「2歳過ぎても言葉が出ない」構音障害と診断された息子の成長記録【体験談】

「うちの子、周りの子と比べて言葉の発達がゆっくりかも…」
そう感じたことはありませんか?
一般的に男の子は女の子に比べると言葉の発達がゆっくりと言われることもあり、「そのうち話すようになるだろう」と、様子を見ているお母さんもいるかもしれません。
当時の私も、不安に感じてはいたけれど
「男の子はそんなもん!」
「そのうち話し出すから様子見でいいよ!」
「子どもによって差があるから心配しなくて大丈夫!」
周りからそう言われて安心していたんです。
でも、2歳を過ぎてもなかなか言葉が出てこない息子を見て、不安は募るばかりでした。
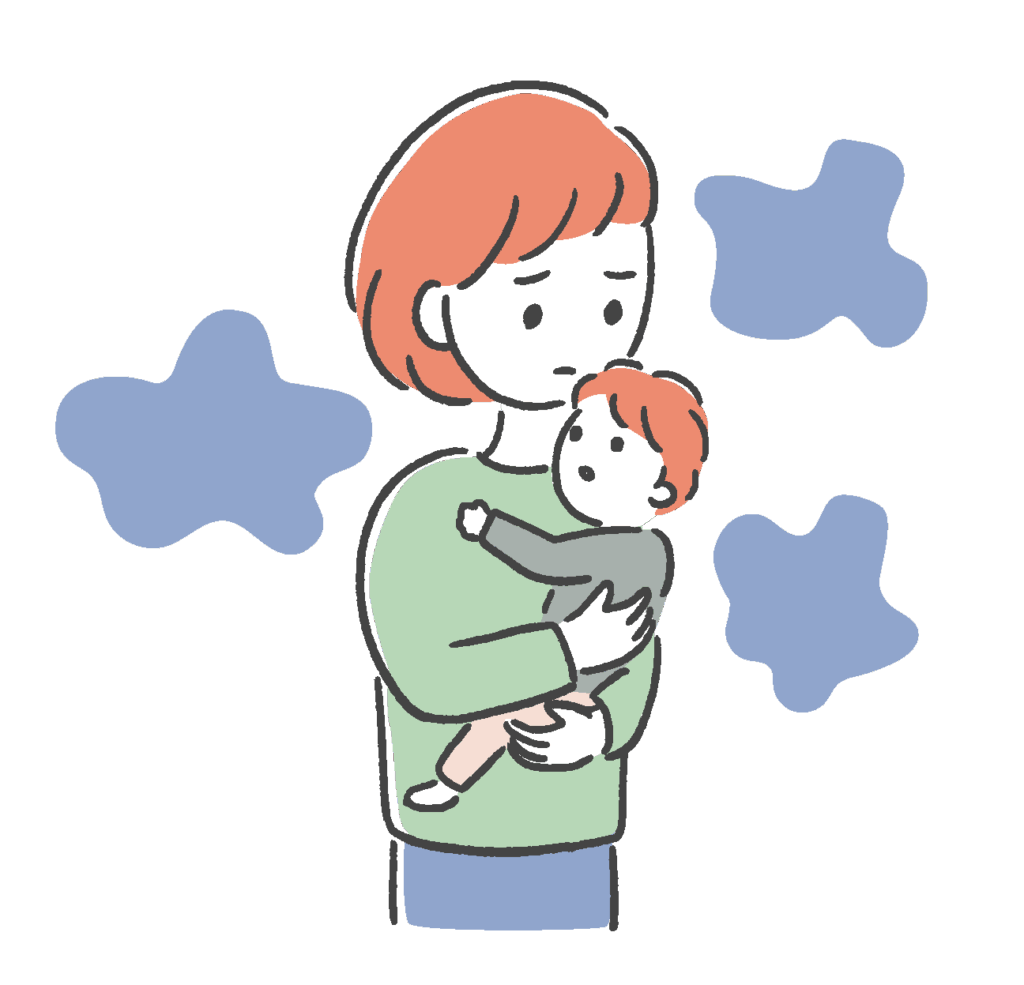
言葉の遅れを指摘された息子
そんな中、たまたま別件で小児科を受診した際、先生から言葉の遅れを指摘され、大学病院の発達外来を紹介されたのです。
そこから始まった大学病院での検査の日々。
知能検査、発達検査、聴覚検査など、様々な検査を受けましたが、特に問題は見当たらず、「構音障害」という診断を受けました。
構音障害とは
構音障害とは、音を作る(発音する)際に、特定の音をうまく出すことができない状態を指します。
例えば、
- 音の置き換え: 「さかな」を「しゃかな」や「たかな」と言う(例:「さ」→「しゃ」、「さ」→「た」)。
- 音の歪み: 特定の音が、本来の発音とは少し違う、聞き慣れない音に聞こえる
- 音の脱落: 言葉の中の特定の音が抜けてしまう(例:「りんご」を「んご」と言う)
- 音の添加: 本来ない音を言葉に付け加えてしまう(例:「いす」を「いすう」と言う)
構音障害の原因は様々で、
- 機能的な原因: 発達の過程で、舌や唇、顎などの動かし方をうまく習得できていない
- 器質的な原因: 唇や舌の形、歯並びなど、生まれつきの体の構造に問題がある。
具体的には、以下のようなものが考えられます。 - 口唇裂(こうしんれつ)・口蓋裂(こうがいれつ): 生まれつき唇や口の中の天井(口蓋)が割れている状態。
- 舌小帯短縮症(ぜつしょうたいたんしゅくしょう): いわゆる「舌足らず」の原因となる、舌の裏側のひだが短い
- 不正咬合(ふせいこうごう): 歯並びや噛み合わせの異常。
- 聴覚的な原因: 聞こえにくいことが原因で、聞いた正しい音を自分の口でうまく発音できない場合
- 神経的な原因: 脳や神経の損傷により、発音に必要な筋肉の動きがうまく制御できない
子どもの場合、多くは発達の過程で見られる機能的な原因によるものが多いと言われています。
原因を特定し、適切な支援につなげるためには、まずは専門家による診断が大切だと思います。
もし、お子さんの発音で気になることがある場合は、一人で悩まずに、小児科や耳鼻咽喉科、または発達支援センターなどに相談してみることをお勧めします。
発達外来から、療育へ
息子が診断を受けてから、定期的に大学病院の発達外来に通っていました。
ただ、予約を取るのも大変で、長い時間待ったにも関わらず、診察自体は「今はこういう状態ですね」という確認だけで終わることがほとんどでした。
もちろん、専門の先生に診ていただくことは安心につながります。ですが、私の場合、「この子のために、何か具体的な働きかけを始めたい」という気持ちが日に日に増していきました。
そこで、思い切って先生に「療育を受けたいのですが、紹介していただけないでしょうか?」と自分から相談してみたんです。
もしかしたら、当時の私と同じように
発達外来に通っているけれど
「もっと何かできることはないのかな?」と感じているお母さんもいるかもしれません。
そんな時は、遠慮せずに自分の気持ちを伝えてみることが大切だと、私の経験から思います。
「ことばの教室」との出会い
息子は小学校に入学するまでは療育に通い、
入学後は、1年生から2年生までは支援学級。3年生から5年生にかけては、通級へと変わりました。
※通級とは:通常学級に在籍しながら、部分的に特別支援を受けることで、障害を持つ生徒の学習や生活の困難を克服し自立を支援する制度のこと。
息子はこのタイミングで、言葉に特化した「ことばの教室」で支援を受けることになりました。
ことばの教室(言語通級指導教室)とは?
「ことばの教室」をご存知でしょうか?
私は、支援学級の先生に教えてもらうまで、そんな教室があることを全く知りませんでした。
「ことばの教室」とは、言葉の遅れや発音、言葉でのコミュニケーション、聞こえ方に不安があるお子さんのための、特別な指導を目的とした通級指導教室のことです。
息子が通い始めて驚いたのは、言葉の発達で悩んでいるママが思いのほか多いということ。
同時に、私と同じように「ことばの教室」の存在を知らないお母さんも多い印象を受けました。
文部科学省の調査によると、令和4年度には、小学校で16万4,735人、中学校で3万1,553人の児童生徒が通級による指導を受けており
その中でも、言語障害が最も多いという結果が出ています。通級による指導を受けている児童生徒数は年々増加傾向にあります。
確認方法としては以下の方法があります。
- お住まいの市区町村の教育委員会に問い合わせる: 最も確実な情報が得られます。
- お子さんの通っている幼稚園、保育園、学校に相談する: 先生方が地域の情報を知っている場合があります。
- 市区町村のWEBサイトを確認する: 子育て支援に関する情報が掲載されていることがあります。
お住まいの市区町村によって異なると思いますが、私の地域には「ことばの教室」が2ヶ所あり、特別に設けられた学校内で運営されています。
うちの子は教室のある学校とは別の学校に通っていたため「通級」という扱いになり、親の送り迎えが必要でした。また、2ヶ所しかないことや利用希望者が多いためか、誰でもすぐに通えるわけではなく、事前に審査がありました。
私の地域では、いくつかの条件を満たさないと利用できなかったり、利用できる年数も限られています。
どんな子どもが通っているの?
実際に「ことばの教室」には、以下のようなお子さんが通っています。
- 構音の誤り: 「さかな」を「しゃかな」や「たかな」のように、音を間違って発音してしまう。
- 吃音: 言葉の最初が詰まったり、同じ音や言葉を繰り返したり、一つの音を長く伸ばしたりする。
- 言葉の遅れ: 語彙が少なかったり、言葉がなかなか繋がって文章にならなかったりする。
- 難聴: 名前を呼ばれても気づかなかったり、聞き返すことが多かったりする。
息子の場合は、特に構音の誤りと言葉の遅れが目立っていました。
「ことばの教室」では、先生とのマンツーマン指導が中心となるため、お子さんのペースに合わせてじっくりと訓練に取り組める環境でした。
うちの息子は3年間お世話になりました。
学校に行きたくない日があっても「ことばの教室には行きたい!」と言うほど、楽しく通うことができ、息子にとって、心の休憩場所のような存在でした。
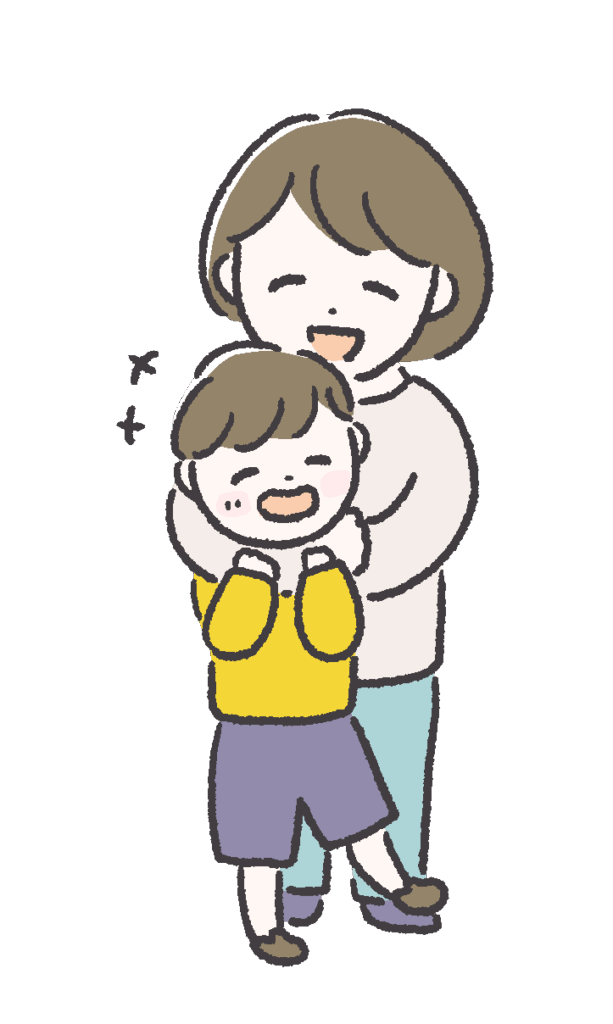
もちろん、まだ言葉の課題はありますが、以前に比べると格段にしっかり話せるようになり、語彙も増えました。何より、自信がついたように感じています。
しかし、ここに至るまで、私自身の心の葛藤もありました。
子どもの発達は、私たち母親の心を大きく揺さぶる問題だからこそ、些細なことで不安になります。
他のお子さんと比べて劣等感を感じて、「うちの子はできないことばかりだ」と自信をなくしたこともありました。
しかし、心の仕組みを学び、自分自身の心の土台を少しずつ築いていくうちに、「この子なら大丈夫!」と心から思えるようになったのです。
子育てにおいては、子どもの発達そのものというよりも、お母さん自身の心の状態が大きく影響します。
また、親の不安は、ダイレクトに子どもに伝わります。お母さんの心が安定していることが、お子さんの心の安定にも繋がっていくんだということを、私は身を持って体感しました。
現在、私たちが提供している、「心の土台構築実践プログラム」は、まさにそんなお母さんたちの心の土台を作るためのプログラムです。
ポポラスには、お子さんの発達で不安を抱えているママがたくさんいます。
誰かに話すだけでも、気持ちが楽になることがあります。
私たちは、決してあなたを一人にしません。一人で苦しまないで下さいね。
子どもの障害、発達の悩みを相談できるカウンセラー▼
https://popolus.jp/counseling_b/

カウンセリングルーム ポポラス/ カウンセラー ▼
https://popolus.jp/about/

